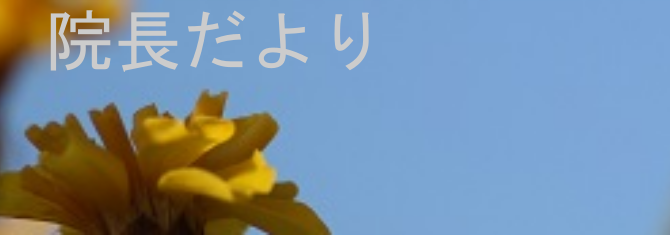東京ディズニーランドに、美女と野獣エリアができ、美女と野獣城ができたというニュースを見た。東京ディズニーランドには、30年くらい前に一度行ったきりだ。東京ディズニーランドのシンボルはシンデレラ城で、世界中のディズニーランドのシンボルがシンデレラ城だと思っている人がいるかもしれない。実は場所によって、お城の種類が違っている。僕はパリのディズニーランドのお城を、てっきり美女と野獣城だと思っていた。しかし、どうやら本当は眠れる森の美女城だったようだ。東京ディズニーランドには1回しか行ったことがないが、パリのディズニーランドに2回行ったことがある。
現在でもパリのディズニーランドはそんなに成功してはいないようだが、1992年の開業時には、「世界の画一化への恐るべきステップだ!」「未開民族の野蛮な現実...文化のチェルノブイリ!」(能登路雅子(2005)、ディズニーの帝国―アメリカ製テーマパークの文化戦略―、立教アメリカン・スタディーズ27)というような言われ方をしていた。
パリのディズニーランドの建設時には、地元の人々から、景観についての苦情もでた。すなわちディズニーランドの見た目がアメリカそのもので、パリ郊外の景観と調和しないというものである。そこで、パリのディズニーランドの建設時には一度施設の色の塗り直しが行われている。現在のディズニーランド・パリの口コミをみても、他のディズニーランドと異なったシックな色合いであったというような評価が載っている。
この塗り直しの指導をしたのが、色彩設計家で当時国立パリ高等装飾美術学校教授でもあったフィリップ・ランクロという人である。ランクロは、「色彩の地理学」という言葉の生みの親で、日本ではこのタイトルの本が、カースタイリング出版(ランクロは車の色彩なども扱っていたため)から、1989年に発行されている。フランス語だと、『フランスの色彩』、『ヨーロッパの色彩』、『世界の色彩』の3部作が、パリのモニトゥール社より出版されている。ランクロは、すべての国や地域は、それぞれの色の文化を持っていることを発見した。特に欧州だと地域の土や石の色が地域の色になっていることを発見した。この考え方に基づいて、パリ郊外の色彩を測定し、それに調和するようにパリのディズニーランドの色の塗り直しが行われている。
景観の色彩や環境の色彩に興味を持っている人々には、ランクロを信奉している人も多い。まあ僕もその一人で、パリのランクロの事務所を訪ねた。説明するのが難しいが、事務所の中はほぼ真っ白で、事務所の扉の真ん中にガラスで仕切られた棚がはめ込まれていて(アクリルでできた女性のアクセサリー入れを大きくして立てたような)、その仕切り一つ一つにフランス各地のカラフルな土が詰め込まれていた。カッコよすぎてしびれた。
ランクロが地域の色の文化を発見したように書いたが、日本でも伝統的な左官職人さんは、地域の土から土壁の材料を作っていた。したがって、地域の色に特徴があることは、彼らにとっては常識的なことなのかもしれない。左官屋さんで日本各地のカラフルな土を集めている人もいる。僕も少し集めているがそんなにいい色合いにはなっていない。教養教育院では、毎年1回教養教育院研究紀要を出しているが、その表紙の色は、この地域の代表的な土の色(に近い色)になっている。地味だなーと思ってる人も多いと思うが、そういう意味があるのでちょっと我慢してください。
ちなみに写真は、ディズニーランド・パリと美女と野獣の悪役ガストンである。
 |
 |