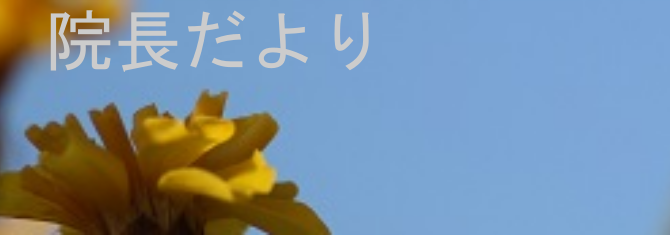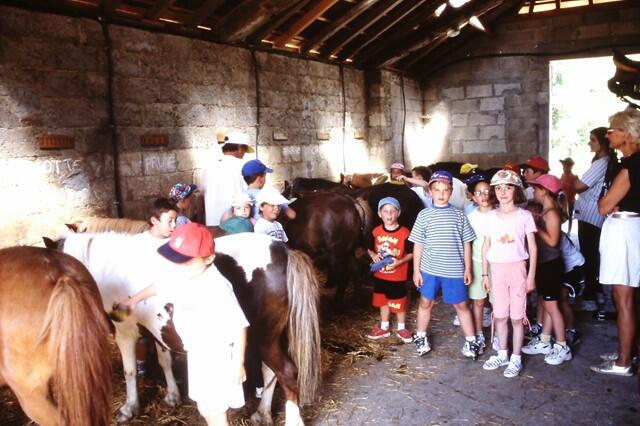教養教育院は、この3月で組織としては存在しなくなります。したがって、この院長ブログも今回で最終回となります。今回のブログでは、「別れ」について書いてみたいと思います。今回のブログのタイトル「長いお別れ」は、もちろんレイモンド・チャンドラーの『長いお別れ』 早川書房 (1976)に倣ったものです。最初にこの本を読んだ時には、この翻訳されたタイトルに非常に魅力を感じました。この本は、2010年に村上春樹によって新訳が出ています。本の表紙ではタイトルを翻訳せず『The Long Goodbye』、内部では『ロング・グッドバイ』としています。村上春樹は、この本に51ページにわたる(Kindleの電子版でですが)訳者あとがきを書いています。村上春樹がこの本のタイトルを『ロング・グッドバイ』としているのは、清水俊二の翻訳で有名な『長いお別れ』と区別をつけるためもあったと書いてあります。村上春樹は、チャンドラーの独特闊達な文体を褒めています。
この小説の中の有名なセリフ「To say goodbye is to die a little」の清水訳は「さよならをいうのはわずかのあいだ死ぬことだ」で、村上訳はほんの少しだけ違っていて「さよならをいうのは、少しだけ死ぬことだ」です。清水訳はとても有名ですが、どうも意味がよくわからないと思っていました。村上訳は、すっきりしています。だって人は「さよなら」を言うたびに死に近づいていきますからね。ただ、村上春樹のあとがきによると、このセリフはフランスの詩人エドモン・アロクールの「離れるのは少し死ぬことだ。それは愛するもののために死ぬことだ。どこでもいつでも、人は自分の一部を残して去っていく」が元ネタだそうです。そうだとすると、僕の解釈はちょっと間違ってる気もします。小学生の頃、学区に国家公務員宿舎があり、同級生が高頻度に引っ越しをしていました。その時に、引っ越してしまってもう会えなくなる友達は、自分にとっては死んでしまうのと同じだと感じていました。これは、ちょっと近い感覚なんじゃないでしょうか?
ところで中島京子に『長いお別れ』 文藝春秋 (2015)という小説があり、2019年に映画化もされています。アルツハイマー型認知症を患った父が、徐々に父でも夫でもなくなっていく様を描いたものらしく(未読)、徐々にお別れしていくことを意味していて、レイモンド・チャンドラーとは無関係にも思えます。この映画に関連して、英語には認知症を『Long goodbye』=『長いお別れ』と呼ぶ表現があるというネット情報が沢山あります。また認知症患者の日記とか、ドキュメンタルフィルムに、「Long Goodbye」というタイトルをつけているものも沢山あります。しかし、そもそもこれらは、チャンドラーの小説から発想して、「Long Goodbye」というタイトルを付けたのではないかと思います。
そしてこの中島京子原作の映画の英語タイトルは、『The Long Goodbye』ではなく『A Long Goodbye』です。ありふれた一つの物語ですよという意味でしょうか?そういえば、僕が若い頃には「The Band」という有名ロックバンドがいて、それをもじった「A Band」という学生バンドがいました。
いよいよこの3月で教養教育院はなくなります。この別れは、は「The goodbye」でしょうか、「A goodbye」でしょうか?それとも、「Long goodbye」になるのか、よもやの「Short goodbye」になるでしょうか?きっとまたお会いしましょう!「サヨナラだけが人生だ」(井伏鱒二)
ちなみに写真は、小屋から旅立つニワトリたちです。