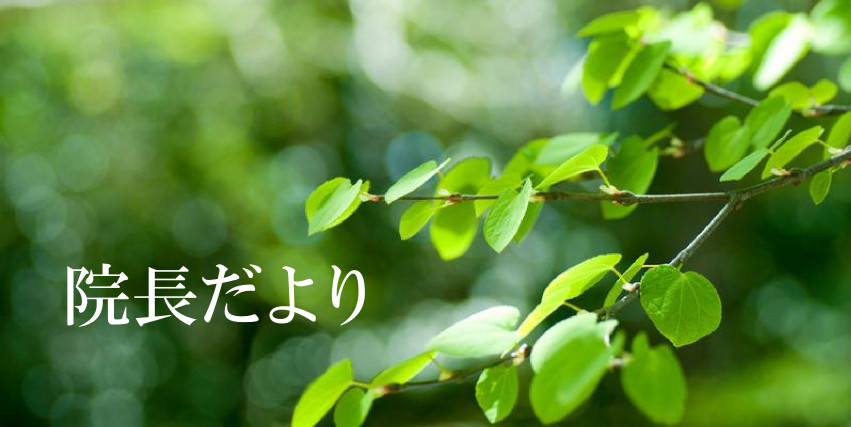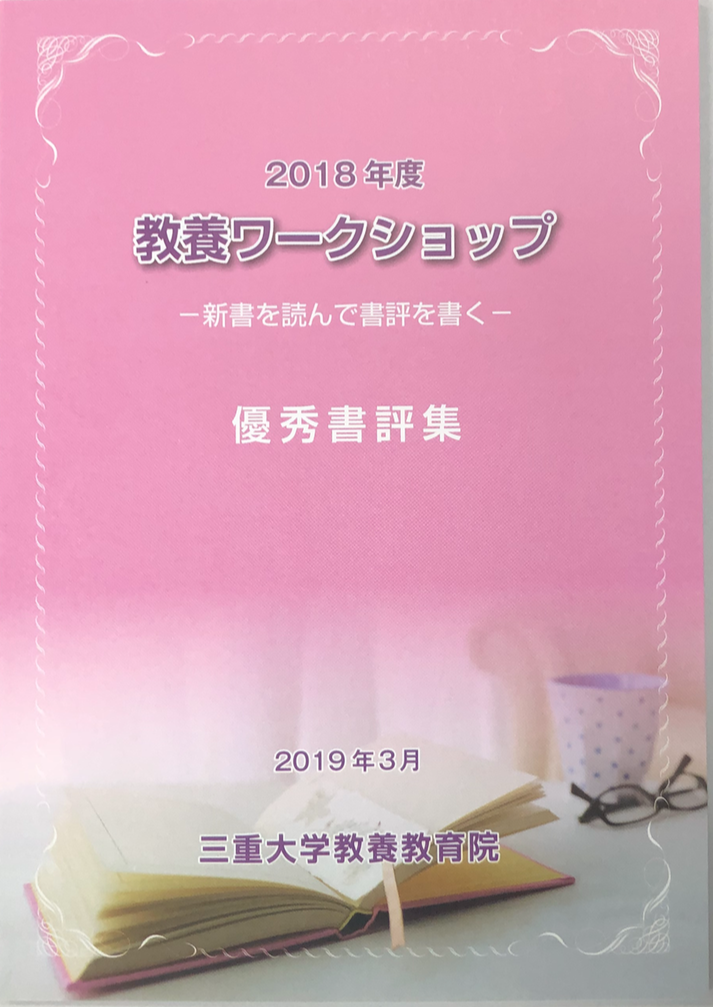上野公園の近くに森鴎外が短編小説『舞姫』を書いたとされる場所があります。現在は旅館になっています。東京滞在の折にジョギングでその前を通ることはあるのですが、残念ながら宿泊したことはありません。旅館のホームページで見る限り、敷地内に森鴎外の旧邸や中庭があり風情のあるところの様です。
その『舞姫』ですが、高校3年生の時に教科書に載っているものを読みました。小説の中に出てくる陰鬱なドイツの描写は、私が初めて見た東ベルリンの光景と重なります。壁が崩壊した直後に偶然ベルリンに行く機会があり、チェックポイント・チャーリー(当時東西ベルリンのパスポートコントロールを行なっていた場所)を通って東側にも行きました。その際に見た、灰色の暗い街の光景です。
さて、『舞姫』の中で、主人公の太田豊太郎が「わが学問は荒みぬ」と述べる箇所があります。数ヶ月前のブログ記事には、昨年実施した教養教育カレッジの担当講師の田中先生と受講生の古市さんとの鼎談の中で、社会に出ても大学に戻って来て体系的な教育を受けるべきだと田中先生が述べられたことを紹介しました。その記事を目にされた田中先生からメールをいただき、なぜそのように意識するようになったのか教えていただきました。高校時代の国語の先生が、上述の『舞姫』の主人公の述懐を「雑学になってしまった」と解釈されたことを受けて、田中先生ご自身は、体系的、組織的学問が不能になり、雑学に入り込む、とその当時の講義メモに書き残されたというのです。
話は少し変わりますが、国立大学が法人化する前年に大学の教職員組合の執行部にいました。当時、何度か衆参両院の関係委員会の傍聴席に座ることがあり、法人化法案の採決の場にも立ち会いました。それまでは欠席していた委員(複数)が採決の場に出てきて大きな声で「賛成」と叫んだ、その荒々しい声が今でも耳に残っています。あれから17年の歳月が流れ、この国の高等教育は大きく変化しました。悪い方へばかり向かっているとは言いませんが、体系的・組織的学問ができるような環境が維持されているかといえば、本学のような地方国立大学に関してはかなり厳しいと言わざるを得ません。外圧もあり、実(雑?)学色がより濃くなっています。この院長だよりの中でも何回か書きましたが、教養とは決して雑学ではなく、現代の細分化された専門知識を俯瞰するために、また、さらに一歩進んで総合的に物事を検討するために必要な体系的な知であると確信しています。
私の研究室のある人文学部校舎はこの4月から改修工事に入ります。4月中旬までに研究室を片付けて一旦出ないといけません。隙間時間に研究室に戻り、大量に溜め込んだものを片付けています。先日も片付けをしながら、三重大学着任当初に指導した学生達が書いたレポート等をパラパラと読んでいました(そんなことしているから片付かないのですが...)。若かったこともあり、膨大な量の課題を与え、今なら卒論に匹敵するようなレポートを書かせていました。それなりの量の資料を読み、レポートや課題をこなしていた当時の学生達と、現在のようにパワーポイントのスライド中心に授業受けている学生達とでは、4年間を通してみると大きな差が生じているのではないか、しばし考え込んでしまいました。大学に入ってきた学生をいかに教育するのか、教養教育と専門教育の双方の立場からの仕組み作りも含めて、今一度考える段階に来ていると強く思います。私のような老兵は消えゆくのみですが、大学を去るまでのあと7年間、できる限りのことをしたいとは思います。
私の教養教育院長としての任期は3月末で終了します。これまで院長だよりをお読みいただきありがとうございました。4月以降は一教員として、新しい気持ちで授業に臨みたいと書きたいところですが、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環で授業の開始が遅れるようです。教育研究を立て直すのにしばらくの時間が必要です。その準備期間として考えるようにします。
 西側からベルリンの壁を壊す!
西側からベルリンの壁を壊す!