専任教員
大井 淳史(おおい あつし)専門分野:生物物理学,食品科学
研究課題:物理および物理化学的視点による食品の製造・保蔵過程の解析
 細胞運動を担っているタンパク質は,非常に小さな,精巧に作られた機械だと考えることができます。筋肉を構成するタンパク質は,分子機械のなかでは最も古くから研究されてきたものですが,化学エネルギーを運動という力学的エネルギーに変換する仕組みについては未解明な部分もあります。マクロなサイズの機械の場合とは異なり,ブラウン運動が無視できなくなるような小さな機械が働く仕組みを理解するには,研究上の様々な戦略が必要になるのです。これまでには比較生化学的な手法が適用可能な魚類を対象として,筋タンパク質の研究をしてきました。意外なことに,こうしたアプローチは食品科学の分野でも有効です。最近では県下の企業との共同研究として,イチゴジャム,スナック菓子,海藻食品などに関する研究を行っています。
細胞運動を担っているタンパク質は,非常に小さな,精巧に作られた機械だと考えることができます。筋肉を構成するタンパク質は,分子機械のなかでは最も古くから研究されてきたものですが,化学エネルギーを運動という力学的エネルギーに変換する仕組みについては未解明な部分もあります。マクロなサイズの機械の場合とは異なり,ブラウン運動が無視できなくなるような小さな機械が働く仕組みを理解するには,研究上の様々な戦略が必要になるのです。これまでには比較生化学的な手法が適用可能な魚類を対象として,筋タンパク質の研究をしてきました。意外なことに,こうしたアプローチは食品科学の分野でも有効です。最近では県下の企業との共同研究として,イチゴジャム,スナック菓子,海藻食品などに関する研究を行っています。
主著[共著]:Nakayama, T., Hatae, K., Kasai, M., Ooi, A. (2017) Seasonal changes in rigor development and flesh texture of wild Japanese sea bass (Lateolabrax japonicus). J. Aquatic Food Product Technology 26:578-592. Ooi, A., Okagaki, T. (2011) Thermal stability of carp actin in its polymerized form. Fisheries. Science. 77: 1053-1059.
太城 康良(たしろ やすら)専門分野:神経発生学、医学教育学
研究課題:(1)胎生期における脳神経の形態発達。(2)成績評価法・授業評価法の妥当性に関する研究。
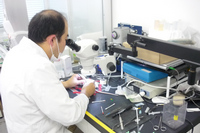 脳の機能は無数の神経細胞の緻密なネットワークの上に成り立っています。この神経ネットワークの発達には外因的な電気活動の有無が大きなカギであると言われています。教育も神経ネットワークの発達を促す良い刺激であってほしいですね。私は医学部では基礎医学(解剖学)やチュートリアル教育(模擬的な臨床症例を用いたグループ学習)を担当しています。特に解剖学は臨床医学の理解に必須の基礎知識ですが、情報量の多さのため、初めて学ぶ者には辟易されがちです。そこで、学ぶ者のモチベーションをいかに持続、向上させるか授業や成績評価の方法も研究しています。分野・学部を問わず、初めて学ぶ者の気持ちを大切に、楽しく、責任ある教育を目指します。
脳の機能は無数の神経細胞の緻密なネットワークの上に成り立っています。この神経ネットワークの発達には外因的な電気活動の有無が大きなカギであると言われています。教育も神経ネットワークの発達を促す良い刺激であってほしいですね。私は医学部では基礎医学(解剖学)やチュートリアル教育(模擬的な臨床症例を用いたグループ学習)を担当しています。特に解剖学は臨床医学の理解に必須の基礎知識ですが、情報量の多さのため、初めて学ぶ者には辟易されがちです。そこで、学ぶ者のモチベーションをいかに持続、向上させるか授業や成績評価の方法も研究しています。分野・学部を問わず、初めて学ぶ者の気持ちを大切に、楽しく、責任ある教育を目指します。
主著:(1)
Oyabu A, Narita M, Tashiro Y. (2013)
The effects of prenatal exposure to valproic acid on the initial development of serotonergic neurons.
International Journal of Developmental Neuroscience
主著:(2)
太城康良、望木郁代、森尾邦正、世宮俊介、白石泰三、堀浩樹 (2014)
ピア評価の導入によるPBL行動評価の改善の試み
医学教育
伊藤 良栄(いとう りょうえい)専門分野:農業情報学,水理学
研究課題:IoTセンサを利活用した農業現場における計測システムの開発
 インターネットの普及により スマホやタブレットなどの情報端末がどこでも利用可能な環境が整備されています。三重大学でもすべての講義室で無線LANが利用できる環境が整備され、新入生はDS(データサイエンス)の授業などで活用しています。しかし、農村や農地は情報インフラの整備が遅れており、スマート農業普及の障害となっています。我々は所属する学会で三重大オタク部隊と呼ばれるマニアックな研究を展開し、電源がないとか、通信手段がないなどの諸問題を克服するための技術開発を行っています。最近ではJST共創の場形成支援プログラムの支援を受け、御浜町の柑橘農園で土壌水分の計測に基づくかんがい用水の最適制御などに関する研究を行っています。
インターネットの普及により スマホやタブレットなどの情報端末がどこでも利用可能な環境が整備されています。三重大学でもすべての講義室で無線LANが利用できる環境が整備され、新入生はDS(データサイエンス)の授業などで活用しています。しかし、農村や農地は情報インフラの整備が遅れており、スマート農業普及の障害となっています。我々は所属する学会で三重大オタク部隊と呼ばれるマニアックな研究を展開し、電源がないとか、通信手段がないなどの諸問題を克服するための技術開発を行っています。最近ではJST共創の場形成支援プログラムの支援を受け、御浜町の柑橘農園で土壌水分の計測に基づくかんがい用水の最適制御などに関する研究を行っています。
主著[共著]:Ryoei Ito and Takamitsu Kajisa(2021) DEVELOPMENT OF PADDY-FIELD WATER LEVEL GAGE CORRESPONDING TO A SENSOR-NETWORK /センサーネットワークに対応した水田水位計の開発, INMATEH - Agricultural Engineering, 63(No.1), 131-136. Ryoei Ito and Chiaki Yamaguchi (2019) A FIELD IMAGE MONITORING SYSTEM BASED ON EMBEDDED LINUX. International Journal of GEOMATE, 17 issue 62, 181-187.
下村 智子(しもむら ともこ)専門分野:比較国際教育学
研究課題:カナダにおけるイヌイットの教育政策、教育課程における資質・能力の涵養
世界のどの国にもその国民を育てるための教育制度が存在します。それらは一様なものではなく、その国の歴史や社会的・経済的・文化的背景、理想とする国民像(市民像)によって、教育の目標や内容、制度等が異なっています。また一方で、グローバル化の進展に伴い、国際的な教育の動向による影響を受けながら、それぞれの国において教育改革が進められています。このように様々な側面が反映されている世界各国の教育について知ることは、その国の文化や人について知ることに繋がるものです。また、比較という視点を持つことにより、日本の学校教育の特徴や日本という国の特質を知ることにも繋がります。
主著[共著]:『21世紀にはばたくカナダの教育』(東信堂、2003)、「先住民の教育における公正に関する一考察-カナダヌナブト準州のイヌイットを事例として-」(『カナダ教育研究』、2006)、『こんなに厳しい!世界の校則』(メディアファクトリー、2011)
長濱 文与(ながはま ふみよ) 専門分野:教育心理学、協同教育
研究課題:学習者の協同に対する認識が学習活動に及ぼす影響
 私たちはそれぞれ、他者と一緒に活動することに対して様々なイメージを持っていると思います。この"他者と一緒に活動すること"を「協同」という言葉にして研究しています。人が「協同」に対してどのように認識しているのか、その認識はどのような環境や経験や出来事により形成されたのか、また、認識の異なる人々が共に活動することで活動自体にどのような影響があるのか、などに興味があります。学習場面や仕事における「協同」活動は課題を達成することに大きな目的があります。そのためにはそれぞれがもっている「協同」へのイメージや認識を超えて、本当の意味で「協同」できるようなグループになることが重要です。そのために必要な考え方やポイントを念頭に置きながら教育や研究を行っています。
私たちはそれぞれ、他者と一緒に活動することに対して様々なイメージを持っていると思います。この"他者と一緒に活動すること"を「協同」という言葉にして研究しています。人が「協同」に対してどのように認識しているのか、その認識はどのような環境や経験や出来事により形成されたのか、また、認識の異なる人々が共に活動することで活動自体にどのような影響があるのか、などに興味があります。学習場面や仕事における「協同」活動は課題を達成することに大きな目的があります。そのためにはそれぞれがもっている「協同」へのイメージや認識を超えて、本当の意味で「協同」できるようなグループになることが重要です。そのために必要な考え方やポイントを念頭に置きながら教育や研究を行っています。
主著:学校で役立つ教育心理学 谷口篤・田村隆宏(編著) 2011 八千代出版 (長濱執筆:6章)
和田 正法(わだ まさのり)専門分野:科学技術史、大学史、作文教授法
研究課題:日本における工学教育の歴史
 大学の教育力を評価することはとても困難です(たとえば、三重大学の教育力は何によって決まるのでしょうか)。これまでは、優秀な教師、立派な施設、活躍した卒業生という、いわゆる良い面を強調してきました。私はそこに、むしろ成績が振るわない学生がどれだけ成長したか、という視点を持ち込みたい。なぜなら、優秀な学生は、放っておいても、他の大学でも成長する見込みが高いからであり、それをその大学の教育力と関連付けるには疑問の余地があるからです。それに対して、いわゆる優秀でない学生が優秀になって卒業したら、それはその大学の教育力のたまものと言ってよいでしょう。こうした教育力の指標を作るために、まずは工学という分野に対象をしぼり、歴史学という手法を用いて、その課題に取り組んでいます。やっていることは、今はまだ、細か~~いことばかりなんですけどね。「三重大学に来て、和田の研究を知って、人生が変わってしまった!」――学生さんにこんなことを言ってもらえるようになりたいと思っています。
大学の教育力を評価することはとても困難です(たとえば、三重大学の教育力は何によって決まるのでしょうか)。これまでは、優秀な教師、立派な施設、活躍した卒業生という、いわゆる良い面を強調してきました。私はそこに、むしろ成績が振るわない学生がどれだけ成長したか、という視点を持ち込みたい。なぜなら、優秀な学生は、放っておいても、他の大学でも成長する見込みが高いからであり、それをその大学の教育力と関連付けるには疑問の余地があるからです。それに対して、いわゆる優秀でない学生が優秀になって卒業したら、それはその大学の教育力のたまものと言ってよいでしょう。こうした教育力の指標を作るために、まずは工学という分野に対象をしぼり、歴史学という手法を用いて、その課題に取り組んでいます。やっていることは、今はまだ、細か~~いことばかりなんですけどね。「三重大学に来て、和田の研究を知って、人生が変わってしまった!」――学生さんにこんなことを言ってもらえるようになりたいと思っています。
主著:「日本の学士課程における教育の一環としての研究――卒業研究の特徴と課題」(2014)、「工部大学校における化学科の位置付け」(2012)、『作文がうまくなる訓練方法』(2014)。
SOKOLOVSKY, Jesse(サコラヴスキー ジェシー)専門分野:第二言語習得、英語教育、異文化理解
研究課題:第二言語リーディングにおける語認知
 私たちは日々の生活で「文字」に囲まれ、その文字が伝達する諸情報を常に処理しています。一旦文字を読むことができるようになると、逆に無視できなくなります。例えば、「あか きいろ あお」と書かれた紙を見せられ、文字を読まずにフォントの色だけを言うという指示があっても、「あか、きいろ、あお」と答えたり通常より時間がかかってしまうことが一般的です。
私たちは日々の生活で「文字」に囲まれ、その文字が伝達する諸情報を常に処理しています。一旦文字を読むことができるようになると、逆に無視できなくなります。例えば、「あか きいろ あお」と書かれた紙を見せられ、文字を読まずにフォントの色だけを言うという指示があっても、「あか、きいろ、あお」と答えたり通常より時間がかかってしまうことが一般的です。
世界の言語には様々な文字体系がありますが、私たちはどのようにあらゆる文字を処理しているのでしょうか。外国語を読んでいる時に、母語話者と同じ処理過程を用いているのか、それとも自分の母語の処理過程を応用しているのか。また、読むスキルが高くなるに連れ、処理過程はどのように進化していくのか。このような課題の解明を目指しています。
主著[共著]:Different cultures different interpretations: Incidents and reflections with focus on Japan. (Nagoya University, 2005)
Language Learning Handbook 2018. (Nagoya City University, Institute for Advanced Education and Research, 2018)
特任教員
荒野 章彦(あらの あきひこ)専門分野:生成文法(統語論)
研究課題:自然言語における移動現象
 私たちが普段使用している日本語は自由語順言語と言われ、様々な語順が許されます。例えば、「太郎が花子に手紙を送った」と言うこともできますし、「花子に太郎が手紙を送った」とも言えます。他にも違った語順を思いつきますよね。こういった語順変化が移動現象の代表的な例です。そして、日本語話者としてこの二つの文の間には何らかの関係があるということも理解できると思います。
私たちが普段使用している日本語は自由語順言語と言われ、様々な語順が許されます。例えば、「太郎が花子に手紙を送った」と言うこともできますし、「花子に太郎が手紙を送った」とも言えます。他にも違った語順を思いつきますよね。こういった語順変化が移動現象の代表的な例です。そして、日本語話者としてこの二つの文の間には何らかの関係があるということも理解できると思います。
言語学の統語論という分野では、文の構造を明らかにすることを目標としています。上に挙げた二つの文は構造的にどういった関係にあるのか。また、日本語で観察される移動現象は他の言語で観察される移動現象とどのように異なるのか。こういったことを主なテーマとし、ことばの性質について研究しています。
論文:Arano, A. (2022) "Reconsidering Multiple Scrambling in Japanese." Journal of East Asian Linguistics 31. Arano, A. (2021) On the Size of Spell-Out Domains: Arguments for Spell-Out of Intermediate Projections. In The Size of Things I: Structure Building, Language Science Press.
岩宮 努(いわみや つとむ)専門分野:英語学(構文文法)、認知言語学、コーパス
研究課題:句動詞および派生語に生じる構文
 中高までで教わる学校文法は、英語力の土台を築く上で非常に重要です。しかし、言語というものは、必ずしも「正しい文法」によってのみ成り立っているわけではありません。英語に限らず、非文法的に見える表現が日常的に使われていたり、厳密な文法に従っていても意図がうまく伝わらなかったりする場面は少なくありません。私はこのように、学校文法では説明が難しい語法や構文、特に句動詞(phrasal verbs)や派生語(derived words)にみられる構文を中心に研究しています。具体的には、コーパスと呼ばれる過去の語彙や表現を集めた大規模データベースを活用し、句動詞や派生語からなる表現が現代英語のどのような場面で使われているかを調査することで、実用性の高い「伝わる英語」とは何かを探っています。また、ChatGPTをはじめとする生成AIやVR(仮想現実)、オンライン辞書、Cambridge系の語学教材、TOEIC・英検・IELTSといった資格試験英語など、英語学習に影響を及ぼすさまざまな要因と、英語学との接点にも関心があり、今後は英語学の知見を英語教育にどのように応用できるかという観点からも研究を進めていきたいと考えています。
中高までで教わる学校文法は、英語力の土台を築く上で非常に重要です。しかし、言語というものは、必ずしも「正しい文法」によってのみ成り立っているわけではありません。英語に限らず、非文法的に見える表現が日常的に使われていたり、厳密な文法に従っていても意図がうまく伝わらなかったりする場面は少なくありません。私はこのように、学校文法では説明が難しい語法や構文、特に句動詞(phrasal verbs)や派生語(derived words)にみられる構文を中心に研究しています。具体的には、コーパスと呼ばれる過去の語彙や表現を集めた大規模データベースを活用し、句動詞や派生語からなる表現が現代英語のどのような場面で使われているかを調査することで、実用性の高い「伝わる英語」とは何かを探っています。また、ChatGPTをはじめとする生成AIやVR(仮想現実)、オンライン辞書、Cambridge系の語学教材、TOEIC・英検・IELTSといった資格試験英語など、英語学習に影響を及ぼすさまざまな要因と、英語学との接点にも関心があり、今後は英語学の知見を英語教育にどのように応用できるかという観点からも研究を進めていきたいと考えています。
論文:岩宮努 (2025)「不変化詞offを伴う句動詞構文の意味と汎用性」JELS 42, 130-139. /岩宮努 (2024)「out-Vに生じる受動者競合構文とZero補部自動詞構文」
日本認知言語学会論文集, 193-204./ 岩宮努 (2024)「不変化詞outに伴って生じる「除去」および「獲得」を表す句動詞構文」JELS 41, 148-157.
奥田 久春(おくだ ひさはる)専門分野:比較・国際教育学、国際教育協力論、教育課程論
研究課題:オセアニア島嶼国の教育と国際協力
 教育制度や教育課程は、その国・地域の社会や文化の中で形成されますが、国際的な影響も受けます。教育政策として積極的に外国から借用するものもありますが、植民地だった国々は宗主国の教育制度の影響を受けたり、開発援助という名目で先進国のモデルが移転されたりということもあります。もちろん一方的に影響を受けるのではなく、様々な相互作用の影響がありますし、国際的な影響を受けつつ自らの教育政策として再構成されるものだという考え方もあります。最近では国や地域の状況に合った教育でありつつ、グローバル化する世界の教育に合わせていくことも課題として認識されるようになっています。
教育制度や教育課程は、その国・地域の社会や文化の中で形成されますが、国際的な影響も受けます。教育政策として積極的に外国から借用するものもありますが、植民地だった国々は宗主国の教育制度の影響を受けたり、開発援助という名目で先進国のモデルが移転されたりということもあります。もちろん一方的に影響を受けるのではなく、様々な相互作用の影響がありますし、国際的な影響を受けつつ自らの教育政策として再構成されるものだという考え方もあります。最近では国や地域の状況に合った教育でありつつ、グローバル化する世界の教育に合わせていくことも課題として認識されるようになっています。
こうした教育における国際的な影響について、教育人材や教材が十分とは言えない小さな島嶼国ではどのような状況なのか関心があります。中でもファア・サモアと呼ばれる独特の伝統文化を重んじつつ、オーストラリアやニュージーランドへ移民を送り出すなど海外とのネットワークが強いサモアで、教育制度や教育課程がどのように形成されているのかについて研究しています。
主著[分担著]「サモアにおける教育開発に関する考察」オセアニア教育学会『オセアニア教育研究』15号(平成21年9月)、「南太平洋の楽園の学校―サモア」二宮晧編著『新版世界の学校』(平成26年1月)
木村 卓人(きむら たくと)専門分野:英語学(言語学)
研究課題:英語句動詞の-er名詞化の研究
 私は英語における句動詞について研究しています。句動詞とは、例えば"pick up"や"help out"のように、動詞(pick、help)と不変化詞(up、out)から成る動詞のことを指します。句動詞には様々な興味深い特徴がありますが、その中でも私は現在、句動詞に"-er"が付いて名詞化した場合の特徴について研究しています。通常、動詞に"-er"がついて名詞になる場合は、例えば"play"から"player"ができるように、"-er"は一つしか現れませんが、句動詞の場合、特に口語では"picker-upper"のように"-er"が複数現れることがあります。このような現象がどのような場合に見られるのか、どのように分析できるのかを研究しています。前述のように"picker-upper"のような現象は口語的であり、さらに話者によって容認できるかどうかの判断が非常にバラバラなので、研究が難しいところではありますが、最近は論文や著書がいくつか出てきており、この現象が注目されはじめているのではないかと思っています。
私は英語における句動詞について研究しています。句動詞とは、例えば"pick up"や"help out"のように、動詞(pick、help)と不変化詞(up、out)から成る動詞のことを指します。句動詞には様々な興味深い特徴がありますが、その中でも私は現在、句動詞に"-er"が付いて名詞化した場合の特徴について研究しています。通常、動詞に"-er"がついて名詞になる場合は、例えば"play"から"player"ができるように、"-er"は一つしか現れませんが、句動詞の場合、特に口語では"picker-upper"のように"-er"が複数現れることがあります。このような現象がどのような場合に見られるのか、どのように分析できるのかを研究しています。前述のように"picker-upper"のような現象は口語的であり、さらに話者によって容認できるかどうかの判断が非常にバラバラなので、研究が難しいところではありますが、最近は論文や著書がいくつか出てきており、この現象が注目されはじめているのではないかと思っています。
論文:
(単著)Notes on Nominalized Phrasal Verbs: A Distributed Morphology Approach to the Difference in Productivity Between Gerunds and Nongerunds" (2022年、Tsukuba English Studies Vol. 40)
(共著)" On the Spatial Meaning of by: A Semantic Network Analysis Based on Schema and Predominance" (2023年、Journal of the English Linguistic Society of Japan Vol. 40 (JELS40))
庄司 貴由(しょうじ たかゆき)専門分野:政治学(政治過程論)
研究課題: 人的貢献・国際平和協力をめぐる政治過程
これまで日本は、国連平和維持活動(PKO)をはじめとする国際平和協力に数万人規模の人員を派遣してきました。現在、日本国民の多くが自衛隊の海外派遣を支持し、定着・拡大しています。戦後日本外交で長らく実現が許されなかった領域が、なぜ、これほどまでに拡大を遂げられたのかを研究しています。ときには困難も伴いますが、周囲のアドバイスなども得ながら試行錯誤を繰り返しているところです。
そうした取り組みにあたっては、書籍はもちろん、外交文書、オーラル・ヒストリーなども交えて進めてきました。いずれも教養教育の授業に組み込み、より現実に根差した政治学の展開を目指します。学生のみなさんが、5W1Hを通じて、独創的な意見を導き出すためのお手伝いをしていければと考えています。
主著:
庄司貴由『自衛隊海外派遣と日本外交―冷戦後における人的貢献の模索』(日本経済評論社、2015年)。
寺田輝介著、服部龍二・若月秀和・庄司貴由編『外交回想録 竹下外交・ペルー日本大使公邸占拠事件・朝鮮半島問題』(吉田書店、2020年)。
庄司貴由「エルサルバドルPKO派遣への道程―国連エルサルバドル監視団(ONUSAL)と日本の対応」、日本政治学会編『年報政治学2020-Ⅱ 自由民主主義の再検討』(筑摩書房、2020年12月)。
玉利 健悟(たまり けんご)専門分野:生理学、人体機能学、食品機能学
研究課題:嗅覚・味覚メカニズムの解明、嗅覚障害の治療法の確立
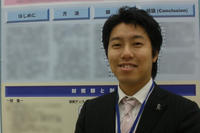 嗅覚・味覚はヒトの心理的変化だけでなく、生理機能を変化させます。これらのメカニズムの解明はこの20年で大きく進歩し、空気や食物中の物質を嗅細胞や味細胞が、どの様な分子機構で情報を脳に伝えるのか明らかになってきました。その一方で、これら障害に悩まれている患者さんはいまだに多く、生活の質を低下させています。この様な問題に対して、私は3つのテーマで研究を行っています。1.嗅細胞に、様々な匂い物質や薬品を投与し、機能への影響を明らかにする。2.嗅覚障害モデルマウスを用いて、薬を投与した際の神経再生を解析する。3.ヒトの味覚検査から味質別の正答率の違いを明らかにする。上記のように細胞、マウス、そしてヒトのレベルまで幅広く研究することで、多方面のアプローチから嗅覚・味覚メカニズムの解明に寄与したいと考えています。
嗅覚・味覚はヒトの心理的変化だけでなく、生理機能を変化させます。これらのメカニズムの解明はこの20年で大きく進歩し、空気や食物中の物質を嗅細胞や味細胞が、どの様な分子機構で情報を脳に伝えるのか明らかになってきました。その一方で、これら障害に悩まれている患者さんはいまだに多く、生活の質を低下させています。この様な問題に対して、私は3つのテーマで研究を行っています。1.嗅細胞に、様々な匂い物質や薬品を投与し、機能への影響を明らかにする。2.嗅覚障害モデルマウスを用いて、薬を投与した際の神経再生を解析する。3.ヒトの味覚検査から味質別の正答率の違いを明らかにする。上記のように細胞、マウス、そしてヒトのレベルまで幅広く研究することで、多方面のアプローチから嗅覚・味覚メカニズムの解明に寄与したいと考えています。
主著[共著]:Suppression and recovery of voltage-gated currents after cocaine treatments of olfactory receptor cells. (Auris Nasus Larynx. 2013)、Blockade of interleukin-6 receptor suppresses inflammatory reaction and facilitates functional recovery following olfactory system injury.(Neurosci Res. 2013)、味覚検査前味質学習が検査に及ぼす影響(日本味と匂学会誌2011)
虹林 桃子 (にじばやし ももこ)専門分野:イギリス ロマン派文学
研究課題:ジョン・キーツの詩作品における音楽的表象
19世紀初頭にイギリスで活躍したロマン派詩人ジョン・キーツの作品における音楽的表象について研究しています。キーツは自然界の音や静寂、感情を音楽のように描写する傾向があり、その表現は詩作品における演出効果の一部として機能していると言えます。この音楽的表象について、ロマン派前後の時代背景との関連性の中で考察することを当面の研究課題としています。
論文:
Keats's "Negative Capability" Figuratively Shown in Hyperion and The Fall of Hyperion(『歴史文化社会論講座紀要』第19号、2022)
Suffering and Beauty in the "Cold": A Study on Keats's "On Visiting the Tomb of Burns" (『人間・環境学』第31巻、2022)
The "Sweet" but "Plaintive" Music in "Ode to a Nightingale" and "Ode on a Grecian Urn"(『イギリス・ロマン派研究』第47号、2023)
福田 知子(ふくだ ともこ)専門分野:生物学
研究課題:植物系統地理学

生物は地球上のあらゆる場所に生息しています。これらの生物の多くは、長い歴史の中で環境の変化に応じて分布域や形を変えながら現在に至ったものです。ある生物やその仲間を詳しく調べることで、それ(ら)がどういう経緯で成立し、分布を広げてきたかが推定できることがあります。私は現在、主にユキノシタ科の植物のうち、北米~北東アジアに分布するシベリアイワブキとその仲間の成立の歴史や関係を推定するため、形態、染色体、遺伝的背景などを調べています。
いろいろな生物が存在していることを「生物多様性」と呼びます。授業では、人間がどのように生物の多様性に気づいて整理してきたか、今後、生物多様性をどう理解し保全していけばいいのかについて考えていきます。また、いろいろな研究例に触れることで、皆さんに生物学の扱う対象や研究の切り口・手法の幅広さを感じていただきたいと思います。
主著(論文等)
Fukuda T., Linnik E. V. (2020) Morphology and habitat of Micranthes fusca (Maxim.) S. Akiyama et H. Ohba (Saxifragaceae). Conservation of biodiversity of Kamchatka and coastal waters XXI: 313-319./Fukuda T., Ikeda H. (2019) A New Chromosome Count for Micranthes nelsoniana var. reniformis (Saxifragaceae) from the Taisetsu-zan Mountains, Hokkaido, Japan. J. Jpn. Bot. 94: 78-81./福田 知子他 (2017)カムチャツカの植物相研究の現状とカムチャツカ[写真付き]植物リストの作成. 日本生態学会誌 67:57-59.
守山 紗弥加(もりやま さやか)専門分野:教育方法学、授業研究、教材開発
研究課題:教育にかかわる時間・空間や雰囲気に関する研究、造形・ものづくり教材の開発
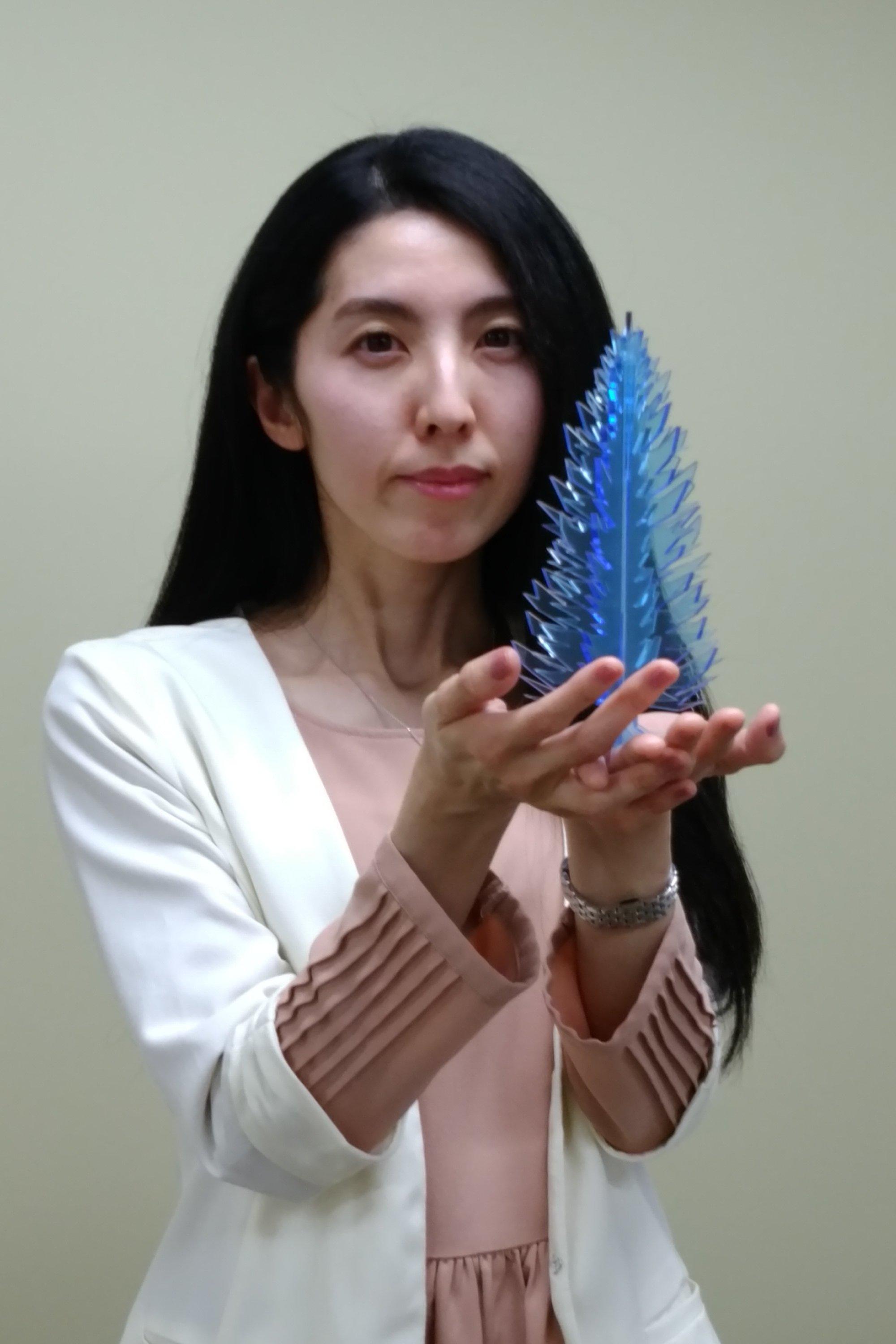 子どもの世界のおもしろさ、不思議さ、豊かさに魅せられ、教室や園における、子どもたちの多様な過ごし方・居方を保障する時間・空間や雰囲気について探究しています。
子どもの世界のおもしろさ、不思議さ、豊かさに魅せられ、教室や園における、子どもたちの多様な過ごし方・居方を保障する時間・空間や雰囲気について探究しています。
研究対象は、誰もが通ってきた「子ども」、みんなが経験する「授業」や「あそび」などですが、そこに広がる世界の奥深さや多様性・多面性に迫るべく、参与観察やインタビューなどの手法を用いた質的研究を行っています。
中でも、造形・ものづくり分野における学びや振る舞い、<あらわし>(表現)、<あらわれ>(表出)に特に強く惹かれ、教材開発や活動・空間デザイン、造形・ものづくり活動のプロセス研究などを進めています。
また、PBL教育におけるシナリオ教材の開発・実践・評価に関する研究にも携わっています。
主著:
「芸術プログラムにおける造形活動形式の提案-「屋台」が育むもの-」(共著),『三重大学教育学部研究紀要』,第67巻,2016
『学生が変わるプロブレム・ベースド・ラーニング実践法』(共訳),ナカニシヤ出版,2016